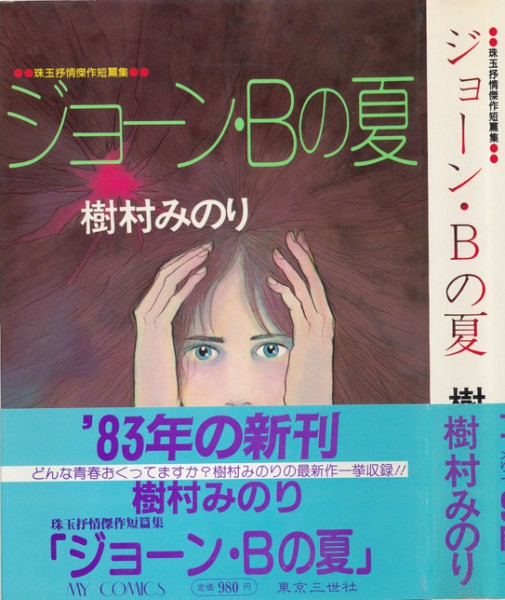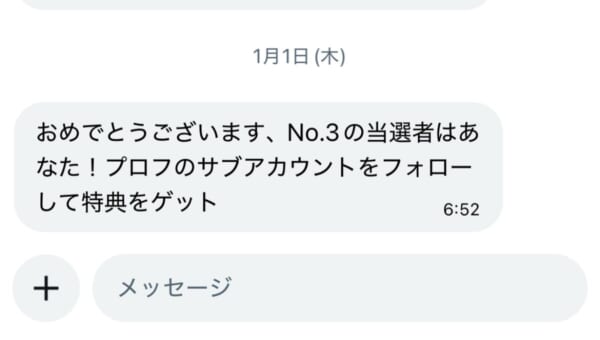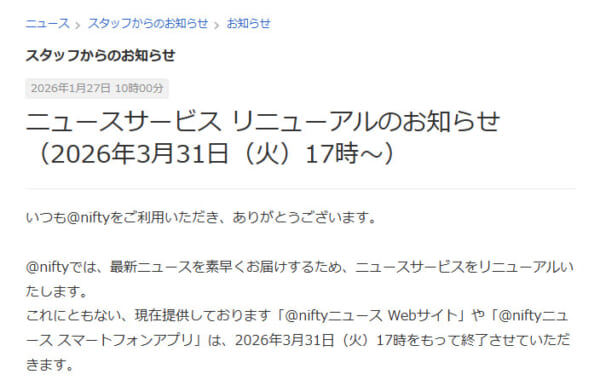「うちの本棚」、今回は樹村みのりの数少ない長編作品から『海辺のカイン』をご紹介いたします。
ジェンダー、親子関係(母娘)、同性愛(レズビアン)を扱った、早すぎた作品ですが、そのテーマはいまも新鮮であり続けています。
『悪い子』もそうだったが、本作で扱ったテーマも社会的な関心がまだ薄かった時期で、「早すぎた」という印象がぬぐえない。また逆に言えば社会的に関心が向けられた後に、再度注目される機会が乏しいということでも残念だ。
樹村みのりは短編の作家と言えて、長編作品は本作のほかには『母親の娘たち』がある程度だ。また本作は樹村みのりの初めての連載作品という記述も某所でみかけたが、初出で示したように連載は飛び飛びであった。樹村みのりの創作ペースを表すいい例だとも言えよう。
本作ではジェンダー、親子関係(ここでは母娘)、同性愛(レズビアン)が描かれている。もっとも深く掘り下げられているのは母娘関係で、これは樹村みのりの作家としてのテーマといってもいいかもしれない。
ストーリーは主に、ふたりの女性の会話によって進められる。
海辺の町に引っ越してきた少女(とはいっても20歳前後と推定される)森 展子は母との関係にトラウマがあり、町で知り合った独り暮らしの女性(こちらはデザイナーで、30代~40代と推定される)佐野と親しくなるにつれ、自分の過去や思いを話し始める。佐野自身は早く両親を亡くしていて、展子のような母娘関係を経験していない。
展子はまた、スカートをはけないと言い、気軽にスカートをはくことができないことに罪悪感を感じるとも言う。女らしい服装ということからジェンダーに言及しつつ、女らしい服装ができないことの原因について母娘関係へと話は進んでいく。
冒頭では聖書からカインのエピソードを引用し、物語上もその事に言及している部分はあるにはあるが、全体としてはその事にあまりこだわっていないようにも思える。ただ、展子と佐野の会話で触れられるカインのエピソードに関する解釈が、本作のラストにも影響しているとするならば、終盤でもカインについての何らかの言及があった方がわかりやすかったのではないかと思える。正直なところ「これで終わっちゃうの?」という印象で、何か言い忘れているような気がしてしまう。これはページが足りなかったとかいうことではなく、樹村みのりが意図的にそうしたのであって読者であるこちらがその意図を汲み取れなかっただけなのだとは思うが、どうしても「何かが足りない」気がするのだ。もっともその喪失感こそが意図だったのかもしれないが…。
講談社から単行本が刊行されたあと、17年を経てヘルスワーク協会の「樹村みのり作品集『少女編』」で再刊行されている。が、それもまた16年も前の話し。とはいえ30年以上が経っても本作のテーマが新鮮に思える現状というのはどういうものなのだろうかという気がしないでもない。
初出:講談社「月刊mimi」昭和55年6、8、11月号、昭和56年1、3月号
書 名/海辺のカイン
著者名/樹村みのり
出版元/講談社
判 型/新書判
定 価/370円
シリーズ名/講談社コミックスmimi(KCmimi-969)
初版発行日/昭和56年5月15日
収録作品/海辺のカイン(I・海に来た少女、II・年上の女性、III・カインの記憶、IV・イニシエーション1、V・イニシエーション2)
(文:猫目ユウ / http://suzukaze-ya.jimdo.com/)