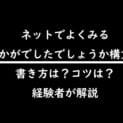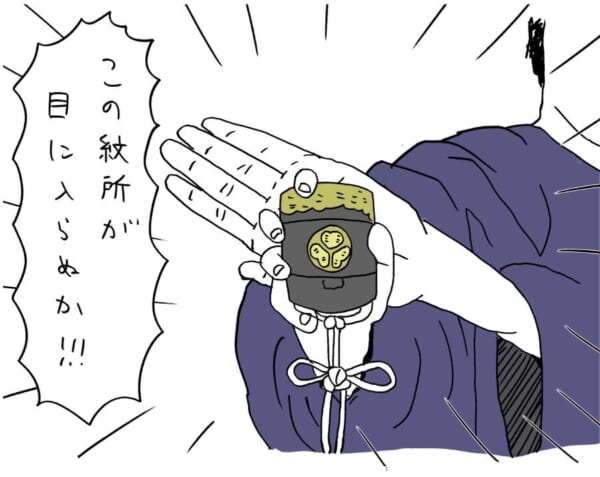今回ご紹介するのは、2014年6月14日に関西地区で先行公開され、7月12日に全国公開された映画『太秦ライムライト』です。
本作はカナダで開催された第18回ファンタジア国際映画祭で最優秀作品賞を受賞し、主演俳優の福本清三が最優秀主演男優賞を受賞しました。
福本清三は1943年2月3日生まれ、1958年に東映京都撮影所に入所した俳優です。
ストーリーは以下の通り。
主人公・香美山清一(演・福本清三)は、京都・太秦の映画撮影所で長年に亘って時代劇の斬られ役を演じたベテランであったが、古き良き時代劇は衰退し、出番がなくなってしまった。そんな中、新人女優・伊賀さつき(演・山本千尋)に乞われ、殺陣の稽古をすることになる……。
本作の劇中世界で描かれた時代背景は、現代の現実世界を反映したものです。時代劇が廃れる様子がそうです。
劇中では、『江戸桜風雲録』というテレビ時代劇の長寿番組が終了する場面があります。同番組は昔、先代尾上清十郎(演・小林稔侍)という俳優が主演し、現在は、先代の息子である当代尾上清十郎(演・松方弘樹)が主演しています。
ここで連想するのは、テレビ朝日で長年に亘ってゴールデンタイムに放送された時代劇枠の最終作『素浪人 月影兵庫』(2007年放送)です。同番組の主演は松方弘樹ですが、昔、松方の父親である近衛十四郎が同名の時代劇に主演していたのです。まるで現実世界の松方と劇中世界の尾上清十郎がオーバーラップするかのようでした。
松方弘樹と同様に現実世界とオーバーラップしていたのが東映剣会の面々です。東映剣会とは、公式ホームページによれば
昭和27年、日本映画黄金期の東映京都撮影所に於いて、殺陣師・足立伶二郎らを中心に殺陣技術の向上・発展と継承を目的に発足した <殺陣技術集団>。
とのことです。東映時代劇を見ると、東映剣会のメンバーが斬られ役だけでなく、同心やら、事件の目撃者やら、色んな役で出演しています。しかしテレビ時代劇の衰退に伴い、時代劇出演も減ってしまいました。『太秦ライムライト』の劇中、斬られ役俳優が刑事ドラマの死体役をやらされる場面は象徴的です。
主演の福本清三をはじめ、『太秦ライムライト』には東映剣会所属の俳優が数人出演しており、本作は東映剣会を描いた映画と言っても過言ではありません。福本と共に斬られ役俳優を演じた木下通博も東映剣会所属で、殺陣師を演じた峰蘭太郎は同会OBです。
峰は『太秦ライムライト』の劇中にずーっと登場していましたが、木下演じる斬られ役俳優は映画の途中で病気になったという設定で、途中から登場しなくなりました。個人的には残念です。
『太秦ライムライト』では、練習のために福本と峰が木刀で打ち合う場面がありますが、東映剣会のメンバー同士が戦うのは珍しく、大変貴重です。というのも、東映剣会メンバーが戦う相手は里見浩太朗だったり西郷輝彦だったり、即ち主役だからです。
私が覚えている限りでは、東映剣会のメンバー同士が戦った前例は『逃亡者おりん2』第10話だけではないでしょうか。『逃亡者おりん2』では副主人公・望月誠之助(演・渡辺大)の上司に当たる家老・水谷守正を、当時東映剣会のメンバーで福本より2歳年上の笹木俊志が演じたからこそ実現できた対決でした。この時は、笹木演じる家老が、敵の忍者・毒空木と戦いました。毒空木を演じた木谷邦臣は福本より5歳年上となります。
後れ馳せながら、ここから本作の感想を3点ほど申し上げたいと思います。
1つ目。本作は劇映画でありながら、部分的にドキュメンタリーかと錯覚してしまう場面がありました。それは、撮影所内を歩く福本を後ろから捉えた一連の場面と、福本が楽屋でメイクする場面です。時代劇の出演者がどのようにして撮影に臨むのかを写した、貴重な記録になっていると言えます。
2つ目は、福本が少年時代にチャンバラごっこに興じたことを回想する場面です。この場面で福本は、少年時代のチャンバラごっこで宮本武蔵役を演じたことを回想し、「我こそは宮本武蔵!」と名乗るのですが、この台詞が一番生き生きしていました。映画の描写はフィクションではありましょうが、「福本は根っからのチャンバラ好きなんだな」と感じさせる場面でした。
3つ目は、本作の肝となる台詞「どこかで誰かが見ていてくれる」です。この台詞は、福本の著書の題名でもあります。実は声優の中尾隆聖も以前、読売新聞でこれに近い話をしていましたし、帝国ホテルの料理長を務めた村上信夫も、同ホテルに就職したばかりの頃、鍋洗い係を一生懸命やって料理人に認められたそうです。「どこかで誰かが見ていてくれる」という台詞は、世の中の多くの人を励ますものだと言えるでしょう。
最後に、昨年(2014年)7月12日に新宿バルト9で催された舞台挨拶における福本の発言をご紹介します。曰く、
「時代劇は東映と言ってる時代じゃない。色んな時代劇があっていい」
本作は、長年に亘って日本人を楽しませた時代劇文化と、それを支えた人々を描いた作品でした。今後も、これらの人々と、新しい世代が、共に新しい時代劇を生み出してくれることを皆で期待しようではありませんか。
(文:コートク)